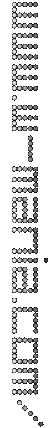痛い青
夕日の残照で、西の空が碧 [あお] くかがやいていた。
雲が、その光に向かって流れてゆく。
重い色が頭上を覆う。川面が深く、青に染まる。
八樹は瞳を伏せた。
梧桐の家を辞したのは何時頃だったろう。
ずいぶん時間が経ったような気もするし、つい先刻のことのような気もする。時計を見るのは面倒だった。
八樹は橋の欄干に肘をついた。
(…どうして)
何故、彼のところへ行く気になったのだろう。
昨日の夜、連絡網が回って。
今朝、気づいたら住所録を手に番地をたどっていた。
近くまで行くと、喪服の人間が大勢いて、すぐに目的地は知れた。
梧桐の家が何代も続いている武術の道場だと、八樹は今日初めて聞いた。そのせいもあってか、弔問客は多かった。
梧桐は、中学の制服姿で式場の前の方に立っていた。
友人だろうか、派手な銀髪の少年と何か話している。
他校生のようだ。制服が違った。
(邪魔しちゃ悪いな)
そう考えてから、胸の内に安堵が湧いたことに気づく。
声をかけない口実が出来たことに、自分はほっとしている。
何も考えずに訪ねてきたものの、彼に掛ける言葉があった訳ではないのだ。
焼香だけして帰ろう。
踵 [きびす] を返しかけた時、ふと梧桐と視線がぶつかった。特に打ちひしがれているようには見えなかったが、唇にいつもの笑みはなかった。
梧桐は、少し驚いた表情になった。
八樹はどういう顔をしていいかわからず、とりあえず頭を下げた。銀の髪の少年がこちらに気づいて振り返ったが、八樹は彼と視線が合う前にその場を離れた。
───母親を喪 [うしな] う、というのはどんな気分なのだろう。
(母さん…)
八樹は自分の母を思った。いっそ。
いっそ母がいなくなってくれたら、自分はどんなに楽になるだろう。
───俺が…。
梧桐にどんな言葉をかけられるというのだろう。
葬儀の場だというのに、八樹は笑い出しそうになった。
自分自身を嗤いたかった。
焼香を済ませて式場を出ようとした時、後ろから声がかかった。
「待って」
振り向くと、小柄な少女が立っていた。同じ中学の冬服が、色素のうすい髪と、きめ細かな白い肌によく映えていた。
「…君は…」
イオリ、という名前は知っている。
校内で、たびたび梧桐と一緒にいるのを見かけた。梧桐の幼なじみの、一年後輩の少女。彼女の長めの髪が、肩先で軽く揺れた。
「勢十郎に、何か言いたいことがあったんじゃないですか?」
琥珀の色をした瞳で、伊織はまっすぐに八樹を見た。
胸の奥で、鼓動が小さく跳ねた。
「…どうして?」
平静を取り繕ったつもりだったが、声が少し上ずった気がした。
伊織はわずかに目を伏せた。長い睫 [まつげ] が、琥珀に淡い影を落とした。
彼女はためらいがちに口を開いた。
「あなたが、勢十郎と同じ目をしていたから」
八樹は川面を眺め、今日、何度目になるか判らない溜め息をこぼした。
───俺には何も言えないよ。
そう言い残して、逃げるようにあの場を去った。
「イオリ、さん」
きれいな子だな、と思う。迷いのない、澄んだ瞳。
あなたが勢十郎と同じ目をしていたから。
(違うよ)
彼女の方が、よほど彼に似ている。自分は、
あんなふうにまっすぐに、誰かを想って動くことはできない。
今日行ったのは、
(梧桐君が、泣いているとでも思った?)
いつも強くて、自分を見下ろしている彼が、多少なりとも弱くなっている所を見たら、安心できるとでも思ったのか?
(───わからない…)
けれど、その想いと同じくらい、彼に弱くなって欲しくないという気持ちがある。
(彼が)
彼が、自分の目標だから。どちらにしても、単なるエゴイズムだ。
八樹は視線を落とした。青い水面。汚れた川。
底にふかく暗いものを孕 [はら] んで、そのくせ表面だけは澄んだ空の青をうつして。
まるで自分自身だ、と考えて吐き気がした。
人形のような、ひとつ年下の少女の顔を思い出す。
自分と梧桐が似て見えたとしたら、きっとこの腐った川が空を映すように、上辺だけのことだろう。
「…最低だ」
八樹は光の残る西の空を見やった。
底深くまで澄んだ、ほんとうの青。彼らに似た、
(…彼に似た)
───届かない青。
針を呑んだように、胸がひどく痛んだ。
(…痛い…)
痛い、と小さく呟く。何故だか声が掠れた。
ぽつり、と手の甲に水滴が落ちた。
(雨?)
川面から吹く風で、やけに頬が冷える。
「!」
冷たい頬に触れてみて、ようやく自分が泣いていることに気づいた。
「…なんで…」
───人は悲しいから泣くのではない。泣くから悲しくなるのだ。
以前、梧桐はそう話していた。
そして、だからいちいち泣くな、と言った。
(…嘘つき)
八樹は、欄干に載せた腕に顔を埋めた。
瞼の裏に、まだ碧い光が灼きついていた。
嘘ばっかりだ。泣いているのに、悲しくならないじゃないか。
(悲しくなんかない…)
ただ痛いだけだ。
棘を刺されたように、身体の奥が疼くだけだ。
「…なんでかなあ…」
なぜ痛いのだろう。
何故、自分は泣いているのだろう。
(なんのために)
───誰のために?
きっと、自分のためだろう。でも、
(彼のために、泣いているんだったらいいのに)
誰かのために、泣けたらいいのに。
痛い、と、もう一度ひとりごちる。
深い青が目に滲みた。
八樹は空を見上げた。ひらり、と白いものが闇をよぎる。
雪が舞いはじめた。